
こんな方々の為のサポートです。

 給料の減額、ボーナスカットなどによって一時的に住宅ローンを支払えなくなってしまったが、家は失いたくない。
給料の減額、ボーナスカットなどによって一時的に住宅ローンを支払えなくなってしまったが、家は失いたくない。  住宅ローンを支払えなくなってしまい、保証会社による代位弁済がなされてしまったが、代位弁済から6か月が経過していない。
住宅ローンを支払えなくなってしまい、保証会社による代位弁済がなされてしまったが、代位弁済から6か月が経過していない。  競売にかけられ差し押さえを受けた状態になったが、やっぱり家は渡したくない。
競売にかけられ差し押さえを受けた状態になったが、やっぱり家は渡したくない。  定期的にある程度安定した収入がある方
定期的にある程度安定した収入がある方  債務の額が多く、任意整理ではどうしても支払えない
債務の額が多く、任意整理ではどうしても支払えない多額の借金を抱え返済ができない人が、裁判所に申し立てて借金を大幅に減額してもらい、減額してもらった債務を、将来の収入から分割(原則3年、利息なし)で支払っていく制度です。
個人再生の1番の特徴は、自宅を維持しながら、住宅ローン以外の借金を整理することができる点にあります。任意整理との大きな違いは、住宅ローン以外の借金元本を大幅に減額することができる点にあります。
個人民事再生手続きには、主に商店主や事業者など個人で事業を行っている人に適用される【小規模個人再生】と、小規模個人再生の対象者のうち、サラリーマンなど将来一定額の収入を継続的に得ることのできる人に適用される【給与所得者等再生】の2種類の手続があります。
小規模個人再生
将来継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、借金(住宅ローン等を除く)の総額が5,000万円を超えない個人債務者が利用できます。
清算価値保証基準(破産した場合の配当を下回らない)の要件を満たし、借金総額に応じた最低弁済基準額を原則3年(5年まで延長可)で弁済すれば、残りの借金は免除されます。
なお、再建計画案の認可には、再生計画案に同意しない債権者が債権者総数の半数に満たず、かつ、その議決権の額が総額の1/2を超えないことが必要です。
清算価値保証基準(破産した場合の配当を下回らない)の要件を満たし、借金総額に応じた最低弁済基準額を原則3年(5年まで延長可)で弁済すれば、残りの借金は免除されます。
なお、再建計画案の認可には、再生計画案に同意しない債権者が債権者総数の半数に満たず、かつ、その議決権の額が総額の1/2を超えないことが必要です。
給与所得者等再生
小規模個人再生の申し立てが可能な人で、サラリーマンなど給与等の変動幅が少なく、定期的な収入が見込まれる場合に利用できます。
可処分所得(自分の収入から所得税、住民税、社会保険料および最低限の生活費を除いた金額)の2年分と小規模個人再生での最低弁済基準額とを比べて多い方 (但し、債権額が3,000万円以下の場合は、上限300万円)を原則3年間で返済すれば、残りの借金は免除されます。
なお、再建計画案の認可には、債権者の同意を必要としません。
可処分所得(自分の収入から所得税、住民税、社会保険料および最低限の生活費を除いた金額)の2年分と小規模個人再生での最低弁済基準額とを比べて多い方 (但し、債権額が3,000万円以下の場合は、上限300万円)を原則3年間で返済すれば、残りの借金は免除されます。
なお、再建計画案の認可には、債権者の同意を必要としません。
個人民事再生のメリット・デメリット
メリット
デメリット
●原則として、所有する財産を手放すことなく、経済的再生をはかれます。
●自己破産に比較して職業の資格制限(※)がありません。
※…自己破産の場合、会社の取締役や監査役、保険外交員、警備員、損害保険代理店、宅地物取引主任者、証券会社の外務員等の資格が制限されます。
●自己破産に比較して職業の資格制限(※)がありません。
※…自己破産の場合、会社の取締役や監査役、保険外交員、警備員、損害保険代理店、宅地物取引主任者、証券会社の外務員等の資格が制限されます。
デメリット
●手続期間が長く、そのための費用が掛かります。
●将来の収入の一部を返済に充てることなど、手続・申立に関しての条件が高い。
●全ての金融機関から7年間ほど借入ができなくなります。
●将来の収入の一部を返済に充てることなど、手続・申立に関しての条件が高い。
●全ての金融機関から7年間ほど借入ができなくなります。
事務所通信
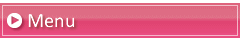
■ 事務所紹介
■ 相続について
■ 遺言について
■ 相続登記
■ 不動産登記
■ 遺言・遺産分割
■ 成年後見
■ 任意整理について
■ 過払い金について
■ 自己破産について