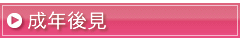
成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な為、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れも十分にあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。そのような事態を避ける為、あらかじめ準備できるなら任意後見制度をおすすめします。
 法定後見
法定後見
認知症などにより、判断能力が不十分となった方を保護するため、家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人などを選任し、後見人などが代理人となって財産管理等を行っていく制度です。
配偶者や親族から家庭裁判所に対して申立をし、後見人などを選任してもらう必要があります。後見人・保佐人・補助人のいずれが選任されるかは、本人の判断能力の状態によって異なります。
 任意後見
任意後見
法定後見とは異なり、まだ判断能力があるうちに自分が将来、認知症や知的障害・精神障害により物事の判断能力が不十分になった時のため、自分の代わりに財産管理などをしてくれる人(任意後見人)を選んでおく制度です。
自分で後見人を選んでおくことができるので、ご依頼者の意志を十分に尊重することができます。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れも十分にあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。そのような事態を避ける為、あらかじめ準備できるなら任意後見制度をおすすめします。
認知症などにより、判断能力が不十分となった方を保護するため、家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人などを選任し、後見人などが代理人となって財産管理等を行っていく制度です。
配偶者や親族から家庭裁判所に対して申立をし、後見人などを選任してもらう必要があります。後見人・保佐人・補助人のいずれが選任されるかは、本人の判断能力の状態によって異なります。
法定後見とは異なり、まだ判断能力があるうちに自分が将来、認知症や知的障害・精神障害により物事の判断能力が不十分になった時のため、自分の代わりに財産管理などをしてくれる人(任意後見人)を選んでおく制度です。
自分で後見人を選んでおくことができるので、ご依頼者の意志を十分に尊重することができます。
法定後見手続きの流れ
本人の判断能力に応じて、後見・保佐・補助の3つに分かれます。
(後見、保佐、補助のそれぞれの説明引用)
どの類型に該当するかは、医師の診断書を元に家庭裁判所が決定します。
現状の確認・診断書の取得
法定後見制度は、既に判断能力が衰えていることが前提となります。
そして、どの程度判断能力が落ちているかについては、医師に診断してもらう必要があります。
医師の診断書は、申立ての際に家庭裁判所へ提出します。
成年後見手続きが始まると、原則、本人の財産は成年後見人が管理することになります。本人が現在どういう財産状況なのかを確認する必要があります。
戸籍や財産関係の資料など家庭裁判所へ提出するための書類を準備し、申立書とともに家庭裁判所へ提出します。
誰を成年後見人の候補者にするのかも決めておきます(申立書に記載された候補者が成年後見人になるケースが大半ですが、誰を成年後見人にするかは裁判所が決定します)。
申立てをした書類をもとに、申立人・本人と家庭裁判所の調査官が面談して詳しく事情を聞き取ります。
特に問題がなければ、候補者が成年後見人として任命されます。
家庭裁判所の審判から、異議なく2週間が経過すると審判が確定し、成年後見人としての業務が始まります。
(後見、保佐、補助のそれぞれの説明引用)
どの類型に該当するかは、医師の診断書を元に家庭裁判所が決定します。
現状の確認・診断書の取得
法定後見制度は、既に判断能力が衰えていることが前提となります。
そして、どの程度判断能力が落ちているかについては、医師に診断してもらう必要があります。
医師の診断書は、申立ての際に家庭裁判所へ提出します。
▼
本人の財産の確認成年後見手続きが始まると、原則、本人の財産は成年後見人が管理することになります。本人が現在どういう財産状況なのかを確認する必要があります。
▼
必要書類の収集・申立書の作成戸籍や財産関係の資料など家庭裁判所へ提出するための書類を準備し、申立書とともに家庭裁判所へ提出します。
誰を成年後見人の候補者にするのかも決めておきます(申立書に記載された候補者が成年後見人になるケースが大半ですが、誰を成年後見人にするかは裁判所が決定します)。
▼
家庭裁判所の調査官と面談申立てをした書類をもとに、申立人・本人と家庭裁判所の調査官が面談して詳しく事情を聞き取ります。
▼
家庭裁判所審判特に問題がなければ、候補者が成年後見人として任命されます。
家庭裁判所の審判から、異議なく2週間が経過すると審判が確定し、成年後見人としての業務が始まります。
事務所通信
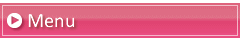
■ 事務所紹介
■ 相続について
■ 遺言について
■ 相続登記
■ 不動産登記
■ 遺言・遺産分割
■ 成年後見
■ 任意整理について
■ 過払い金について
■ 自己破産について