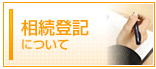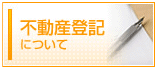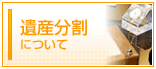遺言書の種類
一定の書式にのっとり自分で全て記入する、もっとも手軽な遺言の基本形ですが、保管の面や本当に本人のものかという効力の面でもめる恐れがあります。 うまく書けないなどの事情で他人の手を借りて記載してしまうと、他人の意思が介在する恐れがあるとみられてしまい、遺言自体が無効になる可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場にて公証人の面前で、証人立会いのもとに遺言の内容を口述したものを筆記してもらう形をとるので、もっとも効果が確実で、改ざんや紛失の心配も無用です。 公証人への手数料など、費用の面では負担になりますが、後日の紛争を防ぐには最も安全で確実な方法です。
基本的には自筆証書遺言と同じになりますが、書いたものに封をして公証役場へ持参して、その存在を証明してもらうというものです。中身を知られたくない、書いた後の保管が心配だ、という方におすすめの方法です。秘密証書遺言は必ずしも自筆によることを要しませんので、ワープロで作成することも可能です。ただし署名は自筆しなければなりません。署名・押印した遺言書を封書にして公証人に提出します。 ※遺言の形式は法律で定められています。形式・内容に不備のある遺言は無効になる場合もあります。 遺言書作成の段階で当事務所にご相談下さい。
どんな場合に遺言を作成するのか?
特に、以下の方は、遺言書作成をお勧め致します。
●子供がおらず、交流のない兄弟がいらっしゃる方
●交流のない異母兄弟・異父兄弟がいらっしゃる方のご両親
●財産を1人残される配偶者に譲りたい方
●離婚した前の配偶者に子供がいる方
●次に発生する相続を見据えた財産の承継を考えたい方
こういったケースで、遺言書がない場合は、下手に財産が遺されていると、相続関係が複雑になってしまい遺産分割協議が難航する傾向があります。
それまで被相続人と全く交流のなかった兄弟姉妹が配偶者に対して相続権を主張してきたり、わざわざ遺産分割のハンコ代を要求したり、無用な費用及び不快感を、遺産を相続するのが通常であろうと思われる方に負担させることになってしまいます。
大事な人に無用な負担を掛けさせないためにも、遺言書作成は絶対にすべきです。
ただ書けばいいわけではなく、遺言は要式行為と言われ、一定の様式を欠いている遺言書は不動産の名義変更(相続登記)に実際に使用できません。
そうならないためにも、事前に司法書士などの専門家に相談し、遺言執行者を定めておくこと等、実際に使える遺言書を書かれることをお勧めします。
死亡後の相続または遺贈による不動産の名義変更について、スムーズに登記手続きをするために弁護士・司法書士を遺言執行者に定めることをお勧め致します。
当事務所では、死亡後にすぐ使える(家庭裁判所による検認手続きが不要になる)公正証書遺言をお勧めしておりますが、遺言に必要な証人2人がいらっしゃらない場合、証人も承っておりますので気軽にご相談下さい。
あなたの大事な人のために遺言作成をしましょう。
●子供がおらず、交流のない兄弟がいらっしゃる方
●交流のない異母兄弟・異父兄弟がいらっしゃる方のご両親
●財産を1人残される配偶者に譲りたい方
●離婚した前の配偶者に子供がいる方
●次に発生する相続を見据えた財産の承継を考えたい方
こういったケースで、遺言書がない場合は、下手に財産が遺されていると、相続関係が複雑になってしまい遺産分割協議が難航する傾向があります。
それまで被相続人と全く交流のなかった兄弟姉妹が配偶者に対して相続権を主張してきたり、わざわざ遺産分割のハンコ代を要求したり、無用な費用及び不快感を、遺産を相続するのが通常であろうと思われる方に負担させることになってしまいます。
大事な人に無用な負担を掛けさせないためにも、遺言書作成は絶対にすべきです。
ただ書けばいいわけではなく、遺言は要式行為と言われ、一定の様式を欠いている遺言書は不動産の名義変更(相続登記)に実際に使用できません。
そうならないためにも、事前に司法書士などの専門家に相談し、遺言執行者を定めておくこと等、実際に使える遺言書を書かれることをお勧めします。
死亡後の相続または遺贈による不動産の名義変更について、スムーズに登記手続きをするために弁護士・司法書士を遺言執行者に定めることをお勧め致します。
当事務所では、死亡後にすぐ使える(家庭裁判所による検認手続きが不要になる)公正証書遺言をお勧めしておりますが、遺言に必要な証人2人がいらっしゃらない場合、証人も承っておりますので気軽にご相談下さい。
あなたの大事な人のために遺言作成をしましょう。
相続人と相続の割合について
| 相続人 | 相続の割合 |
| 配偶者:子 | 配偶者:1/2 子:1/2 |
| 配偶者:直結尊属 | 配偶者:2/3 直系尊属:1/3 |
| 配偶者:兄弟姉妹 | 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4 |
※内縁関係にあった人は、相続の対象とはなりませんが、嫡出でない子(内縁関係にあった人との子)は、相続の対象と認められています。
尚、相続順位は「子」と同じですが、相続分は「実子」の1/2となります。
尚、相続順位は「子」と同じですが、相続分は「実子」の1/2となります。
事務所通信
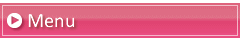
■ 事務所紹介
■ 相続について
■ 遺言について
■ 相続登記
■ 不動産登記
■ 遺言・遺産分割
■ 成年後見
■ 任意整理について
■ 過払い金について
■ 自己破産について